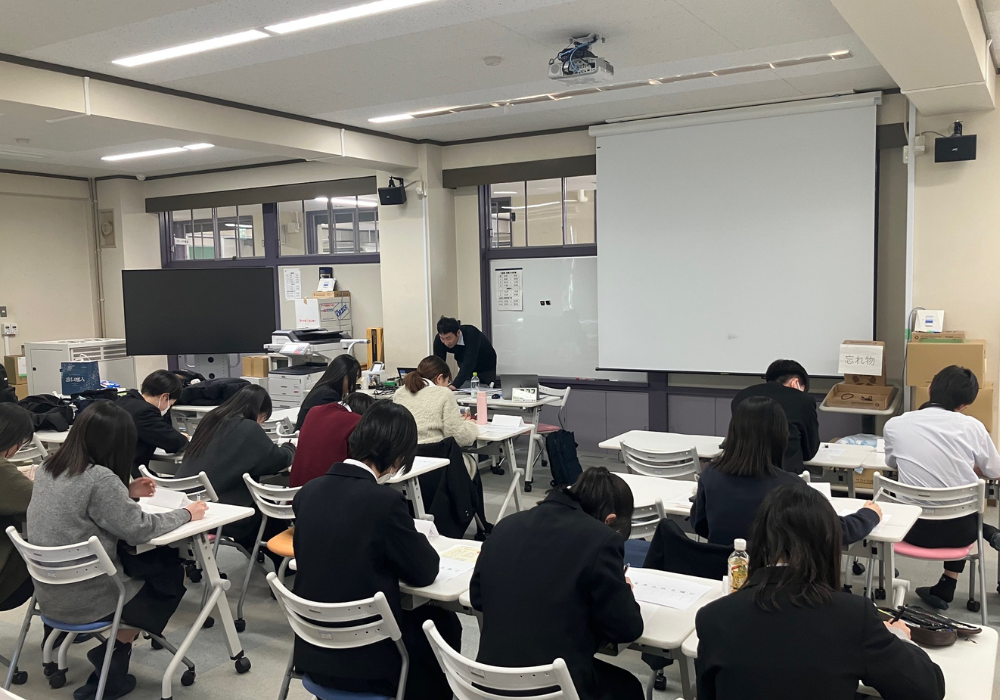2025年3月14日、神奈川県立光陵高校文芸部さんで「ライトハイク教室」を実施いたしました。(日本財団助成事業)令和6年度、最後の詩の授業になります。
これまで、小学校、中学校、高校、シニアと詩の授業を実施して参りましたが、いずれも普段、詩に馴染みのない人に対して、詩の面白さを伝えたいという気持ちで臨んでいました。今回は、すでに「詩の面白さ」を十分わかっている人たちに向けてでしたので、授業とはいえ、共に詩を楽しみたいという気持ちを持って臨みました。
光陵高校文芸部は、顧問に宮﨑先生を迎えて以来、「短歌」に特化して、活動をしています。短歌の様々な全国大会で結果を残してきている、気鋭の短歌集団です。
嬉しいですね。詩を愛する人たちを前にするのは。
古今東西、「詩」というものは、孤独なものです。
まだ俳句や短歌であれば、部活動や結社などで、同じ嗜好の人たちと触れ合う機会もありますが、自由詩を嗜好する者の場合は、なかなか、集まるということもありません。
ですから、最初に皆さんに会った感想は、「嬉しい」です。
あんまり嬉しかったので、身も蓋もない質問を最初に皆さんにしてしまいました。
「詩とは何ですか」
自分が、ずっと考えてきたことなんです。詩を作る人は、自分なりの「詩とは」を持っている。だから、聞きたかったんです。もちろん、詩と同じように、そこに正解も間違いもありません。その人にとっての詩は、色々なのです。以下、出てきた言葉たちです。
詩とは、エモい言葉
詩とは、自由に表現したいもの表現する言葉
詩とは、抽象と具体の狭間
詩とは、自分の思いを伝える手段
詩とは、世界
詩とは、老後の道楽
詩とは、言葉の芸術作品
詩とは、思いを込めた言葉の羅列
詩とは、他人に理解してもらうための言葉
詩とは、自分の人生経験から紡がれる言葉
詩とは、明確な意図を持って書かれた文章
詩とは、言葉
詩とは、自己表現の方法
詩とは、その人の感性が現れる場所
詩とは、言いたいことを言いたいだけいう
詩とは、言葉の広がり
詩とは、形式に捉われない非日常的な言語芸術
最初に答えてくれた生徒さんが「エモい」という言葉を出してくれました。これは、私自身の「詩とは何か」の答えと一緒で驚きました。
「エモい 意味」 と検索に入れます。AIが出す答えは以下です。
「エモい」は、主に若者の間で使われる俗語で、「心が揺さぶられて、何とも言えない気持ちになること」を意味します。
私は、詩とは「心が揺さぶられる」ものだと考えています。言葉でなくても、音楽、風景、建築、料理・・・いろいろな「もの」そして「こと」もあるかもしれない。全部、「詩」です。言葉で表したものを特に「詩」と呼んでいますが、それは、一番シンプルな詩の表現方法だからです。なかなか人の心を揺さぶるまで持っていくのは難しいのですが、不可能ではありません。
詩とは、エモい言葉。
私も、そう、思っています。
今回は、前半と後半の二部制で実施しました。前半が個人戦、後半が団体戦です。
前半で、後半の団体戦のチームメンバーを選抜します。
前半の個人戦では、3題用意して、皆には3回創作してもらいました。
1回目のお題は「その光あふれる陵に」 ※陵(おか)に
これは、光陵高校の校歌の一説から取りました。
2回目のお題は「雨女雨男いて花曇」
これは、私が詠んだ俳句です。短歌の皆さんだから77と結ぶ人が出てくるかと期待して出しました。
3回目のお題は「紙ヒコーキが飛んでいる」
顧問の宮崎先生に出していただきました。
毎回一人ずつ、その言葉を選んだ解説付きで、全員に発表してもらいました。
瑞々しい言葉がたくさん出てきましたが、1編だけ紹介します。
その光あふれる陵に
君の手が星に見えた
私が選んだ、3年生部員さんの言葉です。
なぜ、これを紹介したかったかというと、普段、短歌をされている皆さんにとっては「違和感」を感じる言葉だという指摘が、とても新鮮に思えたからです。
私は、全く、違和感を感じませんでした。
それは、57577のリズムの中で詩を詠んできた人にとって、この、
その光 5
あふれる陵(おか)に 7
君の手が 5
星に見えた 6
最後の「6」が、たまらなく違和感なのでしょう。気持ち悪いんだと思います。
恐らく、
その光
あふれる陵(おか)に
君の手が
星に見えたり
波に見えたり
などにすると、ストンと落ちるのだと思います。
ですが、ライトハイクはそれを許しません。音から解放することの「痛み」だと思っています。その痛みがなくなるまで慣らすことができれば、世界に届けることができると信じています。
事実、私はずっと自由詩をやってきたので、
その光あふれる陵に
君の手が星に見えた
この二行詩になんの違和感もなく、すんなりと受け入れることができます。詩は韻文と呼ばれ、リズムはとても大事な要素ですが、言語を超えてを考えた時に障壁となります。なかなか高い壁ですが、それを打破したい。スマホがあれば瞬時に自国語に翻訳できる時代、スマホがあれば瞬時に世界と言葉を交わせる時代が来たのですから、壁を壊す「時が来た」と考えています。
もちろん、国内の中で、韻文としての短歌を守っていくことは、とても大切なことであるということは言うまでもありません。
前半、3回の個人戦で各回ごとに、顧問の宮﨑先生選、私の選(ライトハイク協会代表)、2名ずつ選びました。この3人と3人の即興チーム同士で、後半の団体選に臨みます。
団体戦の競技は、夏に開成高校・中学校で実践した「ライトハイク・パシュート」
言葉の追いかけっこです。
同じ起句から、3回結んで、最終的に四行詩を作り上げます。
このパシュートの最大のポイントは、3人で1フレーズ(句)を一緒に考えること。
短歌や俳句の団体戦競技がありますが、それらは、一人一人が作った作品を複数出し合って競う形式です。今も昔も世の東西を問わず、詩は一人で作るものでしたから、当たり前と言えば当たり前の形ですが、ライトハイクはそこも打ち破りたい。
詩は一人で作るものだと、誰が決めましたか?
自由詩は、自由な詩であり、詩は自由なのです。だから、常識にとらわれなくていい。
3人でひとつのフレーズを考える。
とても、素敵じゃないですか。
今回、この形を初めて、部員の皆さんにやっていただきました。最初は議論から進めていましたが、どちらのチームも最終的には、3人がまず、それぞれフレーズを作り出し、そこから議論という形に落ち着きました。文芸部さんならではの形だと思います。ただ、これも、せっかく団体戦なのですから、とにかく議論、議論で、1フレーズを生み出す形もあっていいと思います。
こういうアイディア、イメージはどう?
面白いね。こういう風に変えたら、もっと面白くない?
このイメージを、的確に表すにはどういう言葉で描けばいいんだろう。
そんな、三人寄らば文殊の詩も、いつか見てみたいです。
この団体競技「ライトハイク・パシュート」のルールについては、ベースとなるものはありますが、まだ、出来上がっていません。これから光陵高校文芸部さんで試行と話し合いを重ねて、確立できたらと考えています。よって、今回は、最終的に完成した2チームの作品(四行詩)の紹介のみで、このレポートを結びたいと思います。
宇宙猫JA L を捕まえる
ごんたん愛を飼い慣らす
えさは恋バナ、一日五回
丸々太った後に食べます
※ごんたん・・・光陵高校のキャラクター
宇宙猫JA L を捕まえる
こーくーほーってなあに
光喰宝とは、陵の歌詠み
銀河も統べる紙ヒコーキ
※統べる・・・とべる とルビが振られています
顧問の宮﨑先生、光陵高校文芸部の皆さん、インストラクターさん、本当にありがとうございました!
また、光の陵で会いましょう。